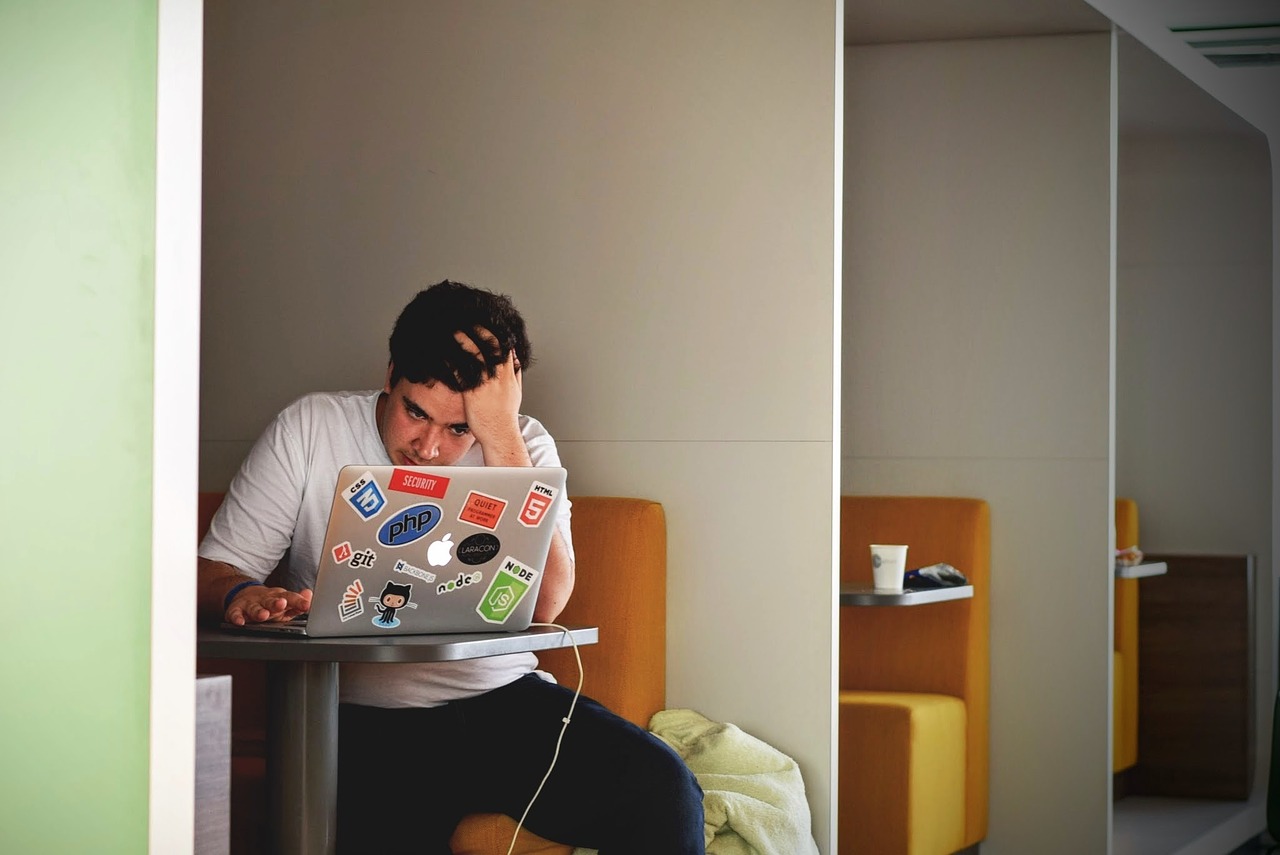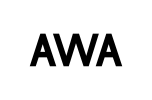クリエイターが創作活動で収入が得られるようになったら、「税金をいくら、どうやって納めればいいのか」という悩みは避けて通ることができません。
実は、税金の納め方は、会社員とクリエイターとでは全然違うということをご存知でしょうか?
今回は、クリエイターはどうやって税金を納めればいいのか、基本的な考え方をご説明します。
おおまかな流れとイメージを掴んでもらうことに主眼を置いているため、だいぶざっくりとした説明となります。
目次
会社員の税金の計算は会社がやってくれる

会社員の場合は、毎月の給与から自動的に税金が差し引かれる「源泉徴収」というシステムがあるため、自分で納税をする必要がありません。
会社が納税額を計算して毎月の給与から天引きし、会社が会社員の代わりに税務署に税金を納めてくれます。
そのため、会社員の方は、給与明細を見て「何か色々と差し引かれているなー」と思うくらいで、自分の税金の金額をどうやって計算して、どこに納めればいいのか、というのをあまり意識したことがないという方も多いかと思います。
クリエイターは確定申告が必要

クリエイターの場合は、自分で税金の金額を計算し、自分で税務署に納めなければなりません。
具体的には、その年1月1日から12月31日までの1年間の売上や経費、所得などから税額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告をしなければなりません。
このことを「確定申告」といいます。
確定申告をするためには1年間の売上や経費の金額について、日々帳簿をつけて記録しておく必要があります。
とりあえず、今は帳簿のつけ方がわからなかったとしても、売上や経費の金額を把握するために、支払調書、納品書、請求書の控え、領収書、レシートなど仕事に関連する書類は何でも捨てずに取っておくようにしましょう。
なお、経費は収入を獲得するために必要な支出しか認められませんが、クリエイターの場合は、一般的な感覚では経費にならないんじゃないかと思うようなものでも経費として認められることがあります。
例えば、イラストレーターが流行りの絵柄を勉強するために買った漫画代や、ミュージシャンがライブで着るために買った洋服代や、ブロガーが喫茶店でブログの更新をする場合の飲食代などでも、それが事業遂行上必要な支出であるならば経費として認められます。
コンビニとかで「レシートいりますか?」と聞かれても「あっ、イイッス」と断ってしまい受け取らない方も多いかと思いますが、意外なものが経費として認められることもありますので、捨てずに取っておけばよかったと後悔しないよう日々の生活の中で購入したもののレシートは何でも取っておくようにしましょう。
納める税金の種類

クリエイターが納める税金には、主に次のようなものがあります。
イメージを掴んでもらうため、詳しい計算方法等についてはこのページでは割愛します。
所得税
確定申告をするうえで一番メインとなる税金です。個人の「所得」、つまり「もうけ」に掛かる税金で、国に納付する国税です。
1年間の「売上」から「経費」を差し引いた「所得」に対して一定の税率をかけて計算します。
おおざっぱなイメージとして、確定申告が必要かどうかは「所得」の金額が38万円を超えているかどうか(副業の場合20万円を超えているかどうか)が目安になります。
住民税
住民税も個人の「もうけ」に掛かる税金で、都道府県及び市区町村に納付する地方税です。所得税の地方税バージョンといったイメージになります。
おおざっぱなイメージとして、住民税を納めるかどうかは「所得」の金額が33万円を超えているかどうかが目安になります。
住民税についてはほとんどの場合、所得税の確定申告をしていれば、あとは自治体が税額を計算してくれるので特に気にしなくても大丈夫です。
(ただし、所得税の確定申告をしていない場合に別途住民税についての申告が必要になることがあります。)
事業税
事業税は、事業の規模がある程度大きくなった場合に道府県に納めなければならない地方税です。
おおざっぱなイメージとして、事業税を納めるかどうかは「所得」が290万円を超えているかどうかが目安になります。
事業税についても住民税と同様、ほとんどの場合、所得税の確定申告をしていれば、あとは自治体が税額を計算してくれるので特に気にしなくても大丈夫です。
消費税
消費税は、消費者が負担する税金を事業者が預かって、事業者が消費者の代わりに納付する「間接税」です。
クリエイターは事業者に該当するので、何かモノを販売したりサービスを提供した場合には、消費者から預かった消費税を代わりに納付しないといけません。
おおざっぱなイメージとして、消費税の納税義務があるかどうかは、2年前の売上高が1,000万円を超えているかどうかが目安になります。
消費税の確定申告をする場合は、所得税とは別の確定申告書を作成することになります。
なお、2年前の売上高が1,000万円以下の場合は「免税事業者」と呼ばれ、消費税込みの金額で売上げていたとしても、消費税を納めなくてもOKです。
確定申告書の提出方法

確定申告書の提出方法は、次の3種類の方法があります。
① 税務署に直接持っていく方法
税務署に直接行けば、税務署の署員に相談をしながら確定申告書を作成することができるので、この方法が一番確実ですが、手間と時間が一番かかります。
確定申告の時期の税務署は激混みなので、時間帯によってはディズニーランドの人気アトラクションくらいの待ち時間は覚悟しなければなりません。
また、税務署はスーパーお役所精神で確定申告期間中であっても土日は基本的にお休みなので、平日に行く必要があります。(一部の税務署では土日でも開庁しています。)
② 税務署に郵送する方法
自分で作成した確定申告書を税務署に郵便で送付する方法です。
なお、郵送の場合は、通信日付印の日が提出日とみなされるので、その年の確定申告期限が3月15日の場合、3月15日の通信日付印が押されていればセーフです。
③ e-Taxを使ってインターネットで提出する方法
インターネット環境があれば、確定申告期間中は24時間いつでも自宅のパソコンから申告ができます。
ただし、事前にマイナンバーカード等の電子証明書の取得とICカードリーダの購入が必要になるので、時間に余裕を持って申告するようにしましょう。